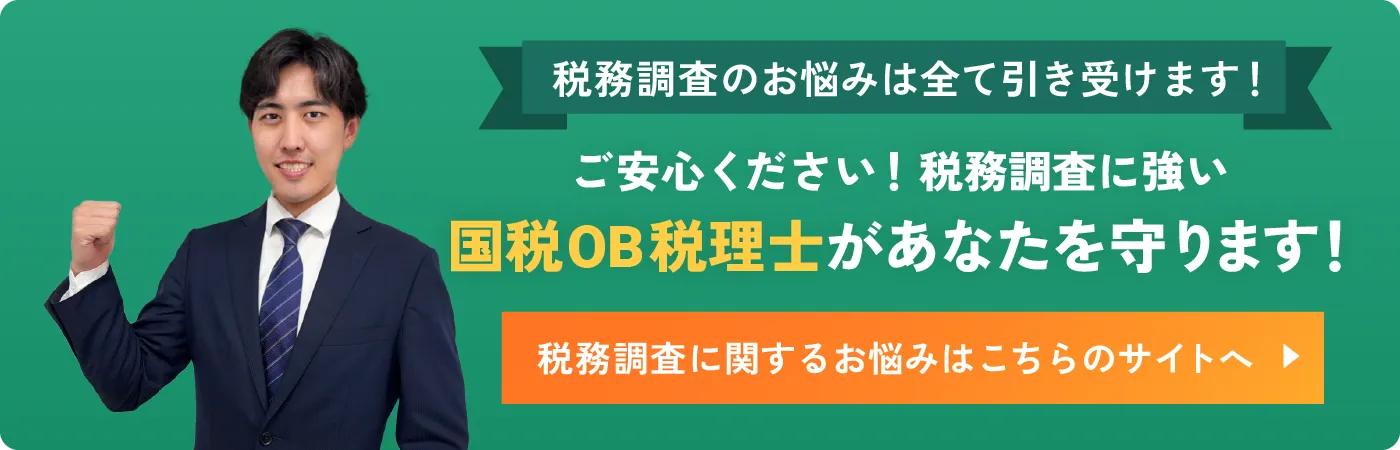税務署から「電話」や「手紙」が届いた方は
税務調査が行われる可能性があります。
「お尋ね」とは、行政指導1つで
税務署からの電話・書面の送付・呼び出しといった”事前通知”のことを指します。
昨今の税務調査において事前連絡がありのものが主流です。
お尋ねがあった場合は、税務調査のターゲットになっていると腹を括りましょう。
・ずさんな節税、どんぶり勘定での申告をした覚えがある…
・顧問税理士にお尋ねの対応経験がない…
・無申告で顧問税理士がおらずどうしていいかわからない…
税務署からの通達内容を実行できない場合、自宅や会社に税務調査が入ります。
適切な対応ができなければ高額な追徴課税がなされ、大きな損失を招くケースも少なくありません。
今回は、税務署による「お尋ね」ついて、理由や対象方法についてお伝えします。
税務署からの「お尋ね」とは
・確定申告をしておらず無申告に該当する
・提出されている確定申告書の内容に間違いや不明点がある
これらのケースを筆頭に税務署が納税者に対して
確定申告の真偽について問い合わせる行政指導のひとつです。
税務署からの封書で届くのが一般的ですが、突然電話がかかってきたり、
税務署への出頭が要請されるケースもあります。
税務調査とお尋ねの違い
税務調査と違ってお尋ねには質問に回答する法的な義務はございません。
また、お尋ねは税務署の職員が直接自宅や事務所を訪問し、
帳簿類などの書類確認を行うこともないといった違いがあります。
ですが、疑いの目を公的機関から受けていることは間違いのない事実になりますので
行政指導だけにとどめるように、しっかりとした対応を行いましょう。
自身で適切な対応が行えない場合は、
税務調査に強い税理士にすぐ依頼をすることをおススメ致します。
【関連コラム】無予告で税務署や国税局が会社や自宅へ税務調査が来た方へ
なぜ、税務署から電話や手紙が届くのか?
①経費に不審点がある
提出した申告書に記載した経費に不審点があると判断された場合に、確認が入る可能性があります。
・同種事業者の平均よりも異常に経費が高額である
・何に使用した経費なのかわからない
といったケースによく見られ、心当たりがある場合は注意が必要です。
本業とプライベートが混同しやすい個人事業主が対象になりやすく
税務署は1度このような疑いを覚えると徹底した確認を行います。
計算に間違いがある、資料に不備がある場合も提出した資料に修正を求められる場合もあります。
②売上額に不審点がある
店舗が流行っていて売上があるはずなのに計上されていない、取引先から支払調書が提出されているのに売上が計上されていないなど、売上額に不審点がある場合が該当します。
・納税事業者になることを回避するために売上高1000万円弱であるという計上を続けている
・急に売上高が爆発的に増加したまたは減少した
・支払調書を加味すると黒字のはずなのに、赤字計上が続いていることに違和感がある
収入があるのに申告をしていない「無申告」の場合にも、連絡が来るケースもございます。
ただし、無申告の場合は突然自宅や会社などに税務署が訪問してくるケースが多いです。
税務のミカタでは、国税局出身の税務調査に強い税理士を中心にご紹介が可能です。
お尋ねはどのような形式でやってくるのか
書面や電話で回答を促すもの
封書にて「申告内容のお尋ね」などの件名が届いた方
電話にて「申告内容について」問い合わせがあった方が該当します。
この場合、確定申告の内容に不明点や記載間違いが考えられるため、回答を促すものです。
適切に回答を行い、税務署の抱く不審点が解消できればそれ以上問題にはならないケースがほとんどです。
書面や電話で解消できない場合は以下のお尋ねが舞い込んでくることになります。
税務署への出頭を求めるもの
資料を用意して税務署へ出頭し、説明を求めるタイプもあります。
この場合、個人のみでの対応が難しくなってきます。
きちんと申告漏れの事実の説明ができて税務署側を納得させる必要があるためです。
書類が用意できない、いよいよ追い詰められてしまったとお考えの方は
今すぐ税務のミカタにお問い合わせください。
実地の税務調査を予定するもの
実地の税務調査の予告として税務署から連絡が来るケースもあります。
このケースは、ほぼ確定で税務調査が入ります。
脱税や申告漏れがほぼ黒であるという証拠を税務署側が握っているためです。
その場合には、税務署と日程調整をして税務調査に対応しなければなりません。
高度な専門知識を必要とする税務調査を個人だけで乗り切るの苦行に等しいです。
税務調査後に修正申告や期限後申告が必要となり、追徴課税される可能性も高くなります。
なお、追徴課税については、追加で支払う金額の最大40%と非常に大きな額になります。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(場合によって15%)の過少申告加算税又は35%(場合によって40%)の重加算税がかかります。
【引用元】申告が間違っていた場合 – 国税庁
税務調査の実施状況とお尋ねが届く確率は?
令和4年12月に公表された法人に対する実地での税務調査件数が約4.1万件でした。
法人の税務調査の確率は概ね1.3%(4.1万件/306万件)となります。
令和4年11月に公表された個人に対する実地での税務調査件数が3.1万件でした。
個人の税務調査の確率は概ね0.5%(3.1万件/653万件)となります。
コロナ前の税務調査率は法人で3.2%、個人事業主で1.1%です。
法人の場合は30社に1社、個人事業主の場合は100社に1社くらいの確率となります。
確率は決して高くはありませんが、法人・個人問わずいつ行われてもおかしくはありません。
お尋ねを無視していたらどうなる?
お尋ねに対して、法的な回答義務は存在しませんが
税務署が疑問や不審点を抱いていることは確実です。
税務署からのお尋ねには、回答期限が存在し
確定申告の内容に間違いがあったとしても
期限内に間違った点を修正申告により対応できるケースがほとんどです。
税務署はこの疑問や不審点を解消するために、お尋ねを無視した方へ
以下の順番で催促を行うことが一般的です。
①督促ハガキが手元に届く
税務署が抱いている疑問や不審点に対して回答を促すハガキが届きます。
②税務署から電話が来る
ハガキを無視した場合は、口頭でのヒアリングをしたいために電話がかかってきます。
これを無視してしまうと、税務調査を行う可能性が高まるので
税務署の不信感を高めないように気を付けましょう。
③税務調査(任意調査)
電話を無視すると、税務署の職員が自宅や事務所を訪問する税務調査が実施される可能性があります。税務調査には二種類あり、この時点で実施されるのは「任意調査」です。「任意」ではあるものの、受忍義務があり、正当な理由なく税務署への対応を拒否した場合には罰則が適用される場合があります。
調査を行う日程は基本的に事前に通知がなされます。
ですが、帳簿書類の改ざんや隠ぺいなどが疑われる場合には、事前通知を行わない無予告での調査が入ることもあります。
※脱税の疑いがある場合は強制調査に
お尋ねを無視したうえで、脱税の疑惑がある場合「強制調査」が実施される場合がございます。
強制調査とは裁判所の令状を得たうえで行われる拒否権のない税務調査のことです。
納税に関連する書類を国税局査察部(マルサ)が押収できる権利を持っています。
強制調査は通常1億円を超えるといった場合に実施されることが多いです。
④追加徴税が行われる
再三のお尋ねを無視して税務調査が行われると、
過少申告加算税や重加算税、延滞税などが課せられ高額な請求を被るリスクが高まります。
お尋ねに回答していたとしても、悪質な隠ぺい・改ざん等が発覚した場合には最大税率45%の重加算税が課せられることもあります。
些細なミスで追徴課税が行われることを避けるためにも、
できる限り早く対応することをおススメ致します。
税務署からのお尋ね(電話・手紙)の対応に不安な方は
税務のミカタへご相談ください
税務署からの電話や手紙に適切に対応する自信がない場合は、
種類に応じて適切な対処方法をアドバイスしてくれる税理士へ相談することをおすすめします。
税務のミカタでは、
国税局に13年以上務めた経験を持つお尋ねや税務調査に強い
経験豊富な税理士を無料で紹介しています。
最短即日で状況に適した税理士を無料でご紹介しております。
この機会に是非1度ご相談くださいませ。

 LINEで24時間受付中!
LINEで24時間受付中!