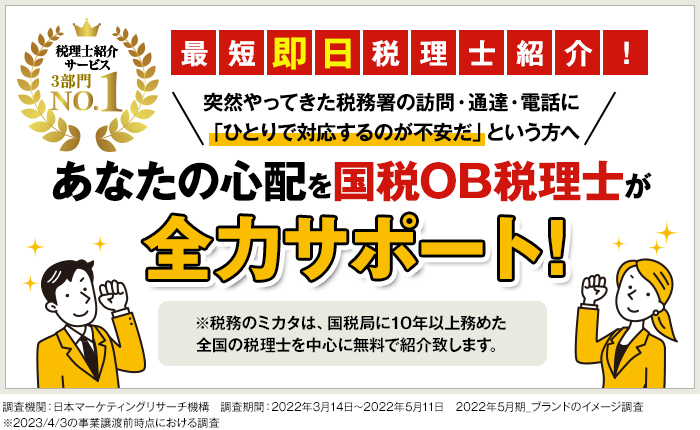マルサ(国税局査察部)とは?
国税局査察部とは、税務調査の中でも
「悪質で高額な脱税が疑われる事案」に対して調査を行う部署です。
一般的には「マルサ」と呼ばれています。
国税局査察部が調査を行う際には、
裁判官の許可を受領し、調査致します。
つまり強制調査を行うために令状を取得し、捜索差押を強制的に実行するのです。
そんな国税局査察部が来るのは、悪質かつ高額な脱税の疑いが濃厚なケースです。
追徴課税も行いますが、主な目的は「刑事告発」です。つまり国税局査察部が来たということは、
将来的に刑事告発されて脱税犯として処罰される可能性が高いです。
査察部(マルサ)の強制調査への対応方法とは?
ある日突然事業所へ「国税局の査察部」が来たら、
どのように対応すれば良いのでしょうか?
結論、私たちは
なるべく早く、税務調査に強い税理士と弁護士を立てることをお勧めいたします。
その理由は、
「査察調査」と一般的な「税務調査」の
違いにあります。
主な違いは、刑事告発される可能性が高く追徴課税額も高額になります。
普通の税務調査でも、
もちろん税理士を立てるべきですが、査察調査はより高度な対応が必要になるのです。
また不利益を小さくするためにも、当初の段階から適切に対処しなければなりません。
今回は国税局査察部とは
いったいどういった部署なのか、
査察部が来た場合の対処方法も含めて解説します。
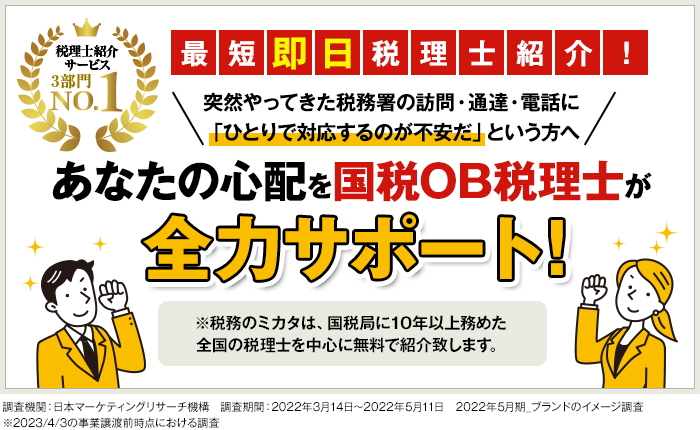
普通の税務調査との違い
マルサ(国税局査察部)による
強制調査と通常の税務調査(任意調査)には具体的にどういった違いがあるのか、みてみましょう。
無予告で突然やってくる
一般的な税務調査(任意調査)は、予告があってから行われるのが原則です。
無予告で調査が入るのは、現金取引の商売などで
「予告すると隠蔽のおそれが高い場合」
などに限られます。
一方で国税局査察部の強制調査に
予告はありません。
ある日突然、令状をもった調査官がやってきて、事業所内の資料を捜索差押えが行われます。
任意ではなく強制的
一般的な税務調査は任意調査なので、
納税者の同意をとって進められるのが原則です。
同意なしに事業所内の物品を
差し押さえられ、引き上げられるわけではありません
(ただし税務調査官には質問検査権があり、納税者には応諾すべき受忍義務があります)。
国税局査察部(マルサ)の場合は逆で、
納税者の許可を得ず、強制調査を行います。
査察調査は犯罪調査の1つに位置付けられます。
なぜ、マルサはやってくるのか
査察調査が来るのは大規模かつ高額な脱税事案
通常の税務調査は小規模の申告漏れや
無申告事案などでも行われますが、
国税局査察部が来るのは大規模で悪質、
高額な脱税事件です。
およそ1億円以上の脱税額が
見込まれる場合にマルサが来る、と言われています。
証拠をある程度つかまれている可能性が高い
国税局査察部が来る場合、事前の内偵調査などを通じてある程度は脱税の証拠を掴まれていると考えるべきです。
資料を示さないと、
裁判所から令状の発布も受けられません。
マルサ(国税局査察部)の調査の流れ
マルサ(国税局査察部)が担当する場合の税務調査の流れは以下のとおりです。
まずは事前に情報収集をする必要があります。会社や自宅に訪問してくるときには非常に大量の情報が収集されていると考えて間違いありません。
調査官が対象者の事業所や自宅などに
やってきて、質問をしたり財産や資料等を確認したりします。
このとき、非常に沢山の場所を細かく
確認するため心理的な恐怖心を抱く
ケースも多いようです。
必要であれば、対象者が取引している
金融機関や取引先などにも照会し、
裏付け証拠を固めます。
取引先などに対する反面調査は今後、
取引先との信用問題になりますので、
反面調査になる前に
税理士で対応するべきです。
マルサの対応は税務のミカタに
お任せください
税務のミカタがご紹介する税理士は、
元国税局出身の税理士です。
つまり税務調査をする側だった人間が、お客様の税務調査をご対応させていただきます。
一般の税理士と元国税局出身税理士は、同じ税理士でも似て非なる職業だと思います。
税務調査の場数と経験値、税務官の動き方まで熟知しております。
そんな精鋭の税理士をあなたのご状況に合わせて、
ご紹介させていただきます。
費用は掛かりませんので、
お気軽にご相談くださいませ。
査察部が来た場合に相談すべき専門家

国税局査察部が来た場合は、税理士だけではなく弁護士にも相談すべきです。
税務関係については
税理士が対応できますが、刑事事件になると弁護士の職域になります。
またすべての税理士や弁護士が査察案件に対応しているわけではありません。
査察案件を取り扱った経験のない人も多数いるので、
専門家の選び方に注意する必要があります。
適切に対応してなるべく不利益を小さくするには、
査察案件の経験豊富でノウハウを蓄積している税理士や弁護士を選ぶべきでしょう。
「税務のミカタ」では、
査察案件に対応している税理士の紹介も可能ですし、調査が進んで刑事事件に発展しそうな場合、
脱税事件に積極的に取り組んでいる弁護士も無料でご紹介できます。
※弁護士法27条、同72条、弁護士職務基本規定13条により紹介料の授受が禁止されていますので紹介先の弁護士からも依頼者様からも報酬は一切頂きません。
ある日突然国税局査察部が来て
対応に困っているなら、
一刻も早く専門家へ相談しましょう。